

推薦者の声

小学生の頃、コーディネーションに出会っていれば
杉山 明美 氏
NPO法人JACOT理事・公認講師
ソウル五輪バレーボール日本代表
NHK解説者
ソウル五輪バレーボール日本代表
NHK解説者
全日本バレーボールのウィングスパイカーの高橋みゆき選手は身長もないなか世界と戦っていました。彼女に幼いころの思い出を聞けば、お父さんから受けていた指導は、まさにコーディネーショントレーニングの考え方を取り入れたものだと思いました。私は、大学から本格的にバレーボールを始めましたが、もし小学生の頃にコーディネーショントレーニングと出会っていれば、もっと選手としてのプレイの幅が広がっていたように思います。是非、ご両親からお子様がコーディネーショントレーニングを体験する機会を作って頂きたいと思います。

ぜひ、お子様に体験させてみてください
宗田 昭弘 氏
区立豊島体育館館長
NPO法人豊島区体育協会理事
NPO法人豊島区バスケットボール協会理事長
NPO法人豊島区体育協会理事
NPO法人豊島区バスケットボール協会理事長
運動やスポーツが本当に嫌いな子っているのでしょうか?コーディネーション道場の子どもたちを2年間傍で見続けてきてそう実感しています。一見「スポーツなんて興味なさそう?」って見受けられそうな子が嬉々としてCOTをしている様子を見て自分まで嬉しくなります。彼らの好奇心旺盛な自主性、何より素晴らしいと思うのはどの子も自信を持っておおらかに育っている姿です。全国のモデル教室が区立豊島体育館で行われることを誇りに感じています。まずはお子様に体験させてみてください。
参加者の声
※昨年度参加者のインタビュー、アンケートより抜粋しました。
子ども
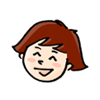 | 前は運動会が好きじゃなかったけど、好きになりました。(教室の良いところは)先生たちが分からないところをやさしく教えてくれて学校の体育に比べて分かりやすいところです。(女の子) |
|---|---|
 | コーディネーションでしかやっていないことを学校で活かせたり、上手になったりして、なんかすごく自信が持てるようになった。(男の子) |
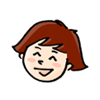 | 運動はもともと好きだったけど、友だちとできるようになった。休み時間はいつも図工室とか音楽室とかで遊んでいたけど、コーディネーションを始めてからは、外でドッチボールとかなぜか参加するようになった。(女の子) |
 | 他のスポーツクラブに2つ入っていたけど、運動はあんまり楽しくないのかなって思っていました。けど、このコーディネーション道場に入って、スポーツの楽しさを実感できてとても気に入りました。(男の子) |
保護者
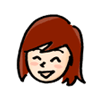 | 運動能力自体は親の私にはまだ目に見えて分かりませんが、最近は体の動かし方が伸びのびしてきたように見受けられます。生活の中では、物事に対する姿勢や友だちとの関わり、また自己肯定感が出てきたのに私が気付くようになりました。(小学3年女子・保護者) |
|---|---|
 | 教室を拝見させて頂いて最も印象に残っていることは性別、年齢の違い、運動能力や興味の違いをそれぞれ持った子ども達の集団の中で勝ち負けや競争・結果に喜び、楽しさを見出すのではなく、共に補う喜びや達成感を子ども達の表情から感じられることでした。スポーツとくに子ども達の中でこのような成果を出すのは正直申して不可能だと思っていましたので大変驚きました。(小学3年女子・保護者) |
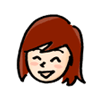 | 秋をすぎたころから特に動きに無駄がなくなってきたように思います。ふざけて遊んでいても、ぶつかったり周りの人に痛い思いをさせるような小さなアクシデントがずっと減りました。少しずつでもできることを増やし、達成する喜びが運動にとどまらず、学校の生活にも現れているように思います。(小学1年女子・保護者) |
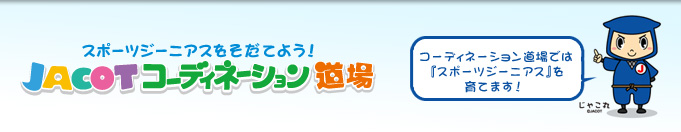
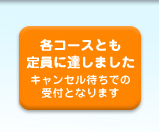
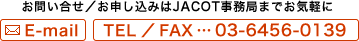
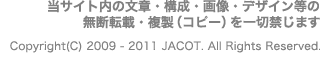
コーディネーション運動は体育やスポーツ活動にとても有効です
池田 延行 教授
前文部省体育官・教科調査官
多様な動きをつくる運動(遊び)パンフレット作成委員